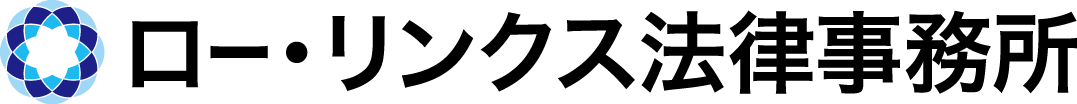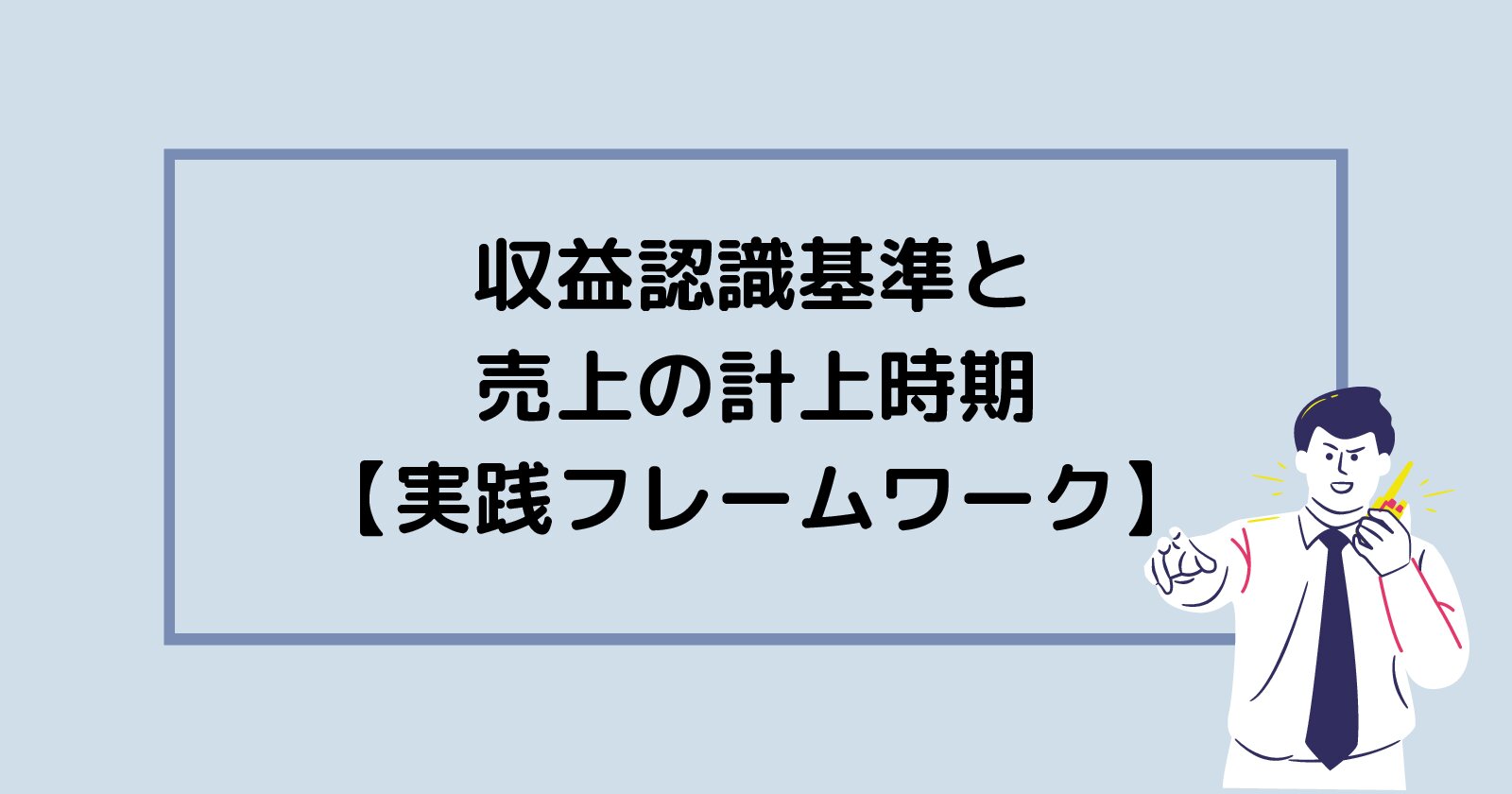上場企業において、監査法人からよく指摘される項目の1つが、売上の計上時期です。その指摘内容は、ほとんどが売上の計上時期が早すぎるというものです。もっとも、上場企業としては、企業側が計上したいと考えている時期に売上計上できた方が有価証券報告書の見た目もよくなりますし、事業計画の管理も楽になりますので、そのような指摘を受けた企業は、できるだけ監査法人の指摘に従った対応はしたくないというのが本音でしょう。
しかし、2021年4月から施行されている収益認識に関する会計基準(以下「収益認識基準」といいます。)は、具体的な事案で検討するには抽象的な規定ばかりで、結局どう考えればいいのかわからず、また、監査法人は、何をどうすれば企業が計上したいと考えている時期に売上計上できるのかについては何もコメントしないため、監査法人が言うとおりに売上計上時期を変更せざるを得ないことがよくあります。
ただ、計上時期の指摘を受けた売上がその企業の売上の相当程度を占めている場合、計上時期を後ろ倒しにしてしまうとインパクトが大きいために、なんとかしたいということもあると思います。結果的にどうにもならないということの方が多いのですが、なんとかなることもあるため、監査法人に指摘されうる事例を紹介しながら、どのように対応するかの考え方をご紹介したいと思います。
売上計上時期の指摘を受けた際の基本的なフレームワーク
ステップ1:収益認識基準上の根拠の確認
監査法人から売上計上時期について指摘を受けた場合、まずすべきことは、監査法人は収益認識基準のどの項に該当すると判断したのかという根拠を確認することです。ただ、注意点として、監査法人に根拠を確認しても間違った根拠を回答してくることがあるため(私は実際に間違いを指摘したことがあります)、監査法人の回答を鵜呑みにせず、自分で収益認識基準を見て考えることも重要です。
ステップ2:収益認識基準の背景ルールの理解
次にすべきことは、なぜその収益認識基準がその時期に売上を計上してはならない(しなければならない)としているのかというルールの背景を理解することです。これは収益認識基準を読んでもよくわからないため、収益認識に関する会計基準の適用指針や、収益認識基準が準拠している国際財務報告基準(IFRS)第15号に関するドキュメントの中から、最初のステップで確認した根拠について書かれている部分を探して読むことをおすすめします。
私がよく参照するのは、KPMG「顧客との契約から生じる収益 IFRS第15号 ハンドブック」とデロイト「顧客との契約から生じる収益 IFRS第15号ガイド」です。
具体的に収益認識基準の背景となっているルールを理解するとはどういうことかは後述しますが、このルールを理解することで、何を変えれば企業が想定する時期に売上を計上できるのかを検討することができます。
ステップ3:取引フローや商品設計の組み立て直し
最後に、ルールの理解をもとに、できるだけ企業が希望する時期に売上を計上できるよう、現在の取引のフローや商品設計を組み立て直します。ポイントは、小手先の変更で監査法人の指摘から逃れられるとは思わないことです。たとえば、契約書における売上代金債権の発生時期と、収益認識基準における売上の計上時期はあまりリンクしていないため、契約書を少し変えるだけでは、売上の計上時期を変更することはできません(監査法人は納得しません)。
ビジネスモデルや商品設計(ひいては顧客のベネフィットのデザイン)を変更するぐらいの大きな変更ができなければ、売上の計上時期の変更はできないと考えておいた方がいいと思います。そのため、検討した結果、そのような変更は現実的ではなく、指摘を受け入れざるを得ないこともありますし、ビジネスの本質的要素を変更せずに、販売戦略や商品設計を変えることで売上計上時期を早められることもあります。
それでは具体的な事例で検討してみましょう。

システムの導入費用やカスタマイズ費用を導入時に売上計上できないという指摘を受けた場合
事例
ある程度以上の規模で、導入後に継続的に利用料を受領するSaaSのようなシステムの場合、システムの導入作業そのものや、システムのカスタマイズ(それをしないとシステムの利用ができないようなもの)についても対価を受領することがあります。しかし、これらの対価は、導入時に売上計上することはできないという指摘を受けます。
法的には導入作業やカスタマイズは、システム利用契約とは別に準委任契約を締結し、契約書で定めた時期にその対価の支払義務が発生して支払いがされますが、それらと会計上の売上計上時期は一致しないためです。
この事例について、上記のフレームワークに基づいて検討していきます。
ステップ1:収益認識基準上の根拠の確認
収益認識基準は、契約の履行義務という概念を採用し、履行義務を充足した時に収益を認識するという原則を採用しています(収益認識基準第16項・第17項)。履行義務というのは、企業が顧客に対して財又はサービスを提供する義務を1つ又は複数に区分して識別する会計上の単位です。法律上の履行義務と、会計上の履行義務は、必ずしも一致しません。
上記事例と関係する履行義務に関する基準は、収益認識基準第32項と第34項に記載があります。
32. 契約における取引開始日に、顧客との契約において約束した財又はサービスを評価し、次の(1)又は(2)のいずれかを顧客に移転する約束のそれぞれについて履行義務として識別する(第7 項参照)。
(1) 別個の財又はサービス(第34 項参照)(あるいは別個の財又はサービスの束)
(2)(略)
34. 顧客に約束した財又はサービスは、次の(1)及び(2)の要件のいずれも満たす場合には、別個のものとする(適用指針[設例5]、[設例6]、[設例16]、[設例24]及び[設例25])。
(1) 当該財又はサービスから単独で顧客が便益を享受することができること、あるいは、当該財又はサービスと顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を享受することができること(すなわち、当該財又はサービスが別個のものとなる可能性があること)
(2) 当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できること(すなわち、当該財又はサービスを顧客に移転する約束が契約の観点において別個のものとなること)
システムの導入作業やカスタマイズは、顧客がその後システムを利用できるようにするために必要な活動であり、それらの作業から単独で顧客が便益を享受することができるわけではないため、履行義務にはあたらないと判断されます。
弁護士的には、導入作業とその後のシステム利用料に関する契約は別個の契約であり、履行義務も、導入作業やカスタマイズにおける義務とシステムを利用させる義務は別個だろうと考えてしまうのですが、会計上は別個の履行義務とは考えない、ということです。
したがって、導入作業やカスタマイズに関する費用は、それらの作業が完了した時点では売上計上ができず、システム利用中に計上することになります。
ステップ2:収益認識基準の背景ルールの理解
上記事例に適用される収益認識基準を確認したので、次はなぜこのようなルールになっているのかを理解します。
先ほど、収益認識基準は履行義務を充足した時に収益を認識するという原則を採用していると書きましたが、収益認識基準がベースとしているIFRS第15号は、企業が顧客に対して財又はサービスを移転すること(その財又はサービスの本質的要素はなにか)と、それと交換で企業が得られる対価の経済的実質を重視します。すなわち、契約という形式は参考にしつつも、その取引において提供される財又はサービスと、その対価の実質を見て、収益として認識すべきかを判断するということです。
上記事例の場合でいうと、導入作業やカスタマイズをした上で顧客にシステムを利用させることがこの取引の実質的要素であるため、導入作業やカスタマイズと、システムの利用が実質的に同一の取引であると評価できるのであれば、契約が別々であったとしても、導入作業やカスタマイズに要する費用を個別に売上として計上することはできない、ということです。 逆に考えれば、導入作業やカスタマイズが、システム利用とは実質的に別個の取引であると評価する余地を作れば、その作業の時点で売上を計上できることになります。

ステップ3:取引フローや商品設計の組み立て直し
導入作業やカスタマイズがシステム利用とは実質的に別個の取引であるということは、言い換えれば導入作業やカスタマイズがそれ単独でサービスとして販売することが可能である、ということです。
したがって、純粋にシステム利用のために必要な導入作業(たとえばシステムの初期設定)や、顧客がシステムを利用できるようにするためのカスタマイズの費用は、どうしようもありません。
しかし、システムを上手く使えるようにするための環境を整えることが必要になる場合は、その作業はシステム利用とは実質的に別個の取引であると評価することができることがあります。たとえば、顧客の規程を整備したり、社内セミナーやトレーニングをしたり、システム基盤を構築するような場合です。このような場合であれば、それらの作業を1つのコンサルティング商品としてパッケージ化してしまいます。
これにより、コンサルティング商品がシステム利用とは実質的に別個の取引である、それ単独でもサービスとして売ることができると評価できれば、これまで顧客から受領していた導入作業とカスタマイズの費用は低額か無料にしてしまい、その分コンサルティング費用を受領するようにすることで、売上の計上時期を大幅に早めることが可能です。
ただし、コンサルティングの内容が実質的に純粋にシステム利用のために必要な作業だと評価されてしまった場合は、やはりその時点で売上計上はできないということになりますし、現実的にそのような形でコンサルティング業務を創出できるかは商品ごとに個別の検討が必要になるので、本当にケースバイケースであることはご留意ください。
終わりに
ここまでお読みいただいた方であれば、収益認識基準により売上計上時期を変更するように監査法人から指摘された場合に、売上計上時期を早める方向で検討するためには、収益認識基準(IFRS第15号)を深く理解した上で、新たな商品を創り出すような作業が必要になることがおわかりいただけたと思います。
収益認識基準の判断は、監査法人によってもまちまちだったりしますし、企業の商品・サービスや価格戦略によって検討内容が全く変わるため、かなり難易度は高いのですが、非常にクリエイティブで、私個人としてはかなり好きな部類の仕事です。そして、この記事でご紹介したフレームワークは、実は弁護士の法的思考を会計基準に応用したものですので、会計分野であるにも関わらず、弁護士がバリューを出しやすい領域でもあります。
監査法人に売上計上時期について指摘をされてしまったとか、過去に指摘されて売上計上時期を後ろ倒しにしたが、やはり前倒しできるか検討してみたいという方がおられましたら、お気軽にご相談ください。